🏠 包括同意基準:建築許可を迅速化する重要制度
みなさん、こんにちは。本日最後の投稿も内容も堅いです。
昨日、「どうしてもここは深堀りしておかなくては・・・」と思ったことがあったので、自分の備忘録として記事を書きました。
それではご興味のある方だけどうぞ。
📘 包括同意基準とは?
包括同意基準とは、上記の建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可を迅速に処理するために、各自治体があらかじめ定めた基準です。この基準に適合する場合、建築審査会の個別審査を省略し、迅速に許可を得ることができます。
主な特徴
- 接道義務を満たさない土地に対して、一定の条件を満たすことで再建築が可能となる制度です。
- 自治体ごとに異なり、地域の特性や状況に応じて設定されています。
- 建築審査会の効率的な運営を支援する役割を果たしています。
具体例
- 横浜市:空地幅員1.5m以上かつ延長20m以下であれば許可が得られる可能性があります。
- 東京都:幅員2.7m以上4m未満の道に2m以上接する敷地であれば許可が得られる場合があります。
📘 建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可とは
建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可とは、通常の接道要件(建築物の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たさない土地において建築物を建てる際に必要となる特別な許可のことです。
この許可は、以下のような状況で必要となります:
- 建築物の敷地が建築基準法上の道路に接していない場合
- 建築物の敷地が道路に2m未満しか接していない場合
- 接している道路の幅員が4m未満の場合
この許可を得ることで、通常の接道要件を満たさない土地であっても、安全性や周辺環境への配慮が確認された上で、建築物を建てることが可能になります。
🏛️ 鎌倉市の包括同意基準:詳細解説
目的
- 手続きの簡素化
- 申請者の負担の軽減
基本的な仕組み
鎌倉市建築審査会が建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可に関する同意を求められた場合、あらかじめ一定範囲の計画について包括的に同意を与えることで、個別の審査を省略できるようにしています。
適用対象
交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる建築物
建築物の許可基準について
- この基準が適用される建築物
- 社寺の境内地に接する建築物
- 既存建築物の建て替え
- 一戸建て住宅(兼用住宅を除く)
- 特定の用途や規模の建築物
- 主な基準内容
(1) 床面積の制限
- 200平方メートル以下
- 300平方メートル以下
- 1,500平方メートル以下
- 建て替え前の床面積の1.2倍以内
(2) 階数の制限
- 地階を除いて2階以下
- 一部の一戸建て住宅では、地階を除いて3階以下
(3) 用途による制限
- 社寺の境内地の維持管理に必要なもの
- 一戸建ての住宅(条件付き)
- 特殊な条件
- 通路幅員:1.5メートル以上必要な場合あり
- 防火に関する規定: 耐火建築物・準耐火建築物以外の場合、延焼防止のための措置が必要
- その他の基準
- 自動車車庫に関する特別な基準あり
これらの基準は、建築物の安全性確保や周辺環境との調和を目的としています。 具体的な適用には、建築物の用途、規模、立地条件などを総合的に考慮する必要があります。
特例
包括同意基準に適合する場合でも、特定行政庁が適当でないと判断した場合は、個別に建築審査会の同意を求めることができます。
施行と改正
この包括同意基準は、平成11年5月11日から施行され、その後、何度か改正されています。
🎯 まとめ
包括同意基準は、建築許可の手続きをスムーズにする重要な仕組みです。以下の点に注意が必要です:
- 地域性: 基準は自治体ごとに異なるため、地域の特性をよく理解することが重要です。
- 詳細な条件: 鎌倉市の事例からわかるように、適用には細かい条件があります。自身の建築計画がこれらの基準に適合するか、慎重に確認する必要があります。
- 簡素化のメリット: この基準を活用することで、建築許可の手続きが簡素化され、時間と労力を節約できる可能性があります。
- 個別対応の可能性: すべての案件がこの基準に適合するわけではないため、個別の状況に応じた対応が求められることもあります。
- 専門家への相談: 不明な点がある場合は、必ず自治体や建築の専門家に相談することをおすすめします。
包括同意基準を正しく理解し活用することで、建築プロジェクトをより円滑に進めることができるでしょう。ただし、常に最新の基準を確認し、適切に対応することが重要です。
- この記事が気に入ったら「シェア」をお願いします!
- Tweet
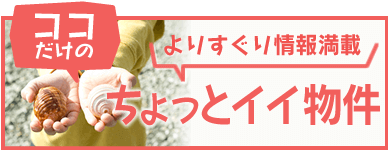

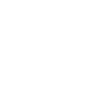
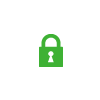


コメントを残す